その人らしい最期を迎えるために





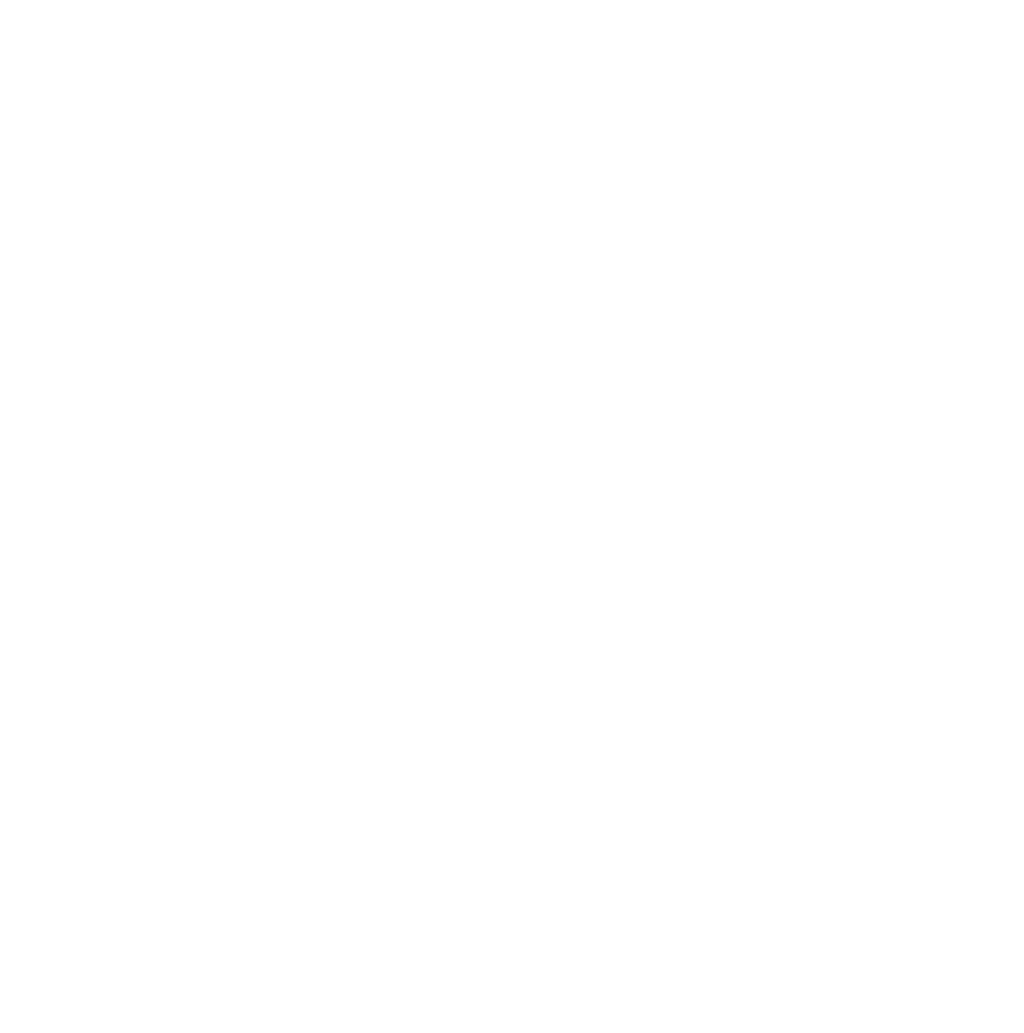 どんな看取りだったかお聞かせ頂けないでしょうか
どんな看取りだったかお聞かせ頂けないでしょうか
私が初めて「看取り」というものを当事者の視点から経験したのは、社会人になって4年目のことでした。
親元を離れて一人暮らしをしていた私は、仕事から帰ってくると母からメールが入っているのに気づきました。
内容を確認すると「おじいちゃんのことで報告しないといけないことがあります。1週間後に入院になりました。肝臓癌と言われました。」と書かれていました。
私は、その絵文字も何もない無機質な文字を見て、一瞬思考回路がついていきませんでした。後から聞いたのですが、当時祖父は異常な倦怠感や気分不良をきっかけに病院を受診し、そこで癌と診断されたそうです。
しかし、診断された時にはすでに転移が進んでおり、何もしなければ半年、治療を受けても1年~1年半という厳しい状況でした。
私は幼い頃、両親が共働きで忙しく、いつも祖父の家に入り浸ってすごしているようなおじいちゃんっ子でした。社会人になってからは目の前の仕事に手一杯で、祖父がそんな状態になっていることも知らず、そんな日が来ることも準備も全くできていなかったのです。
あれよあれよという間に抗がん剤治療の予定が組まれました。祖父の場合は1週間~2週間かけて抗がん剤を投与し、一旦退院。数週間後に再度入院し、抗がん剤を受けるという流れでした。
しかし、治療はなかなか思うようにいきません。抗がん剤というものはがん細胞だけでなく正常な細胞にも攻撃を仕掛けてしまいます。
猛烈な吐き気と倦怠感、味覚障害、免疫力の低下という副作用は常につきまといました。それでも祖父は、少しでも長く家族といられるならと、激しい副作用と闘いながら、治療を継続していきました。
一通り抗がん剤投与の期間が終了した後、検査で抗がん剤の効果を判定しましたが、結果は「明らかな効果はみられない」でした。
肝臓の腫瘍(しゅよう)は大きくなってはいないものの、大腸や肺への新たな転移が見つかったのです。今思えば祖父の気力も段々とすり減っていたのだと思います。
次の抗がん剤治療は、副作用に耐えられず家に帰りたいと漏らしていました。
副作用で倦怠感や吐き気があり食事は食べられず、一生懸命口にいれても味覚障害で味なんてものは分からない。病院という不慣れな環境では、よりストレスとなっていたと思います。
抗がん剤治療を開始して約半年。治療に苦しみながら病院で最期を迎えるよりも、家族と穏やかな時間を過ごしたいと、現状の治療をすべて中止して、完全に緩和ケアへ切り替えることになりました。
家族も私もそれが祖父の最期の願いだと痛感しました。何より生きるために苦しんでいる祖父を見ていたくありませんでした。
自宅に帰ってくると、すぐに在宅診療の先生が現在の症状を緩和する薬を処方してくれました。
祖父も慣れた環境に帰ってきて安心したのか、食事も少しずつ食べられるようになり、家の周りを散歩するようになりました。
しかし、祖父の誕生日会をした翌週、少量ですが吐血をするようになりました。ベッドに横になる時間が増えていき、担当の先生から鎮痛(ちんつう)の点滴をしてもらいました。
いよいよ今夜になるかもしれないと説明を受け、家族全員覚悟しました。夜中、物音がして目を覚ますと祖父が朦朧とした様子で起き上がろうとしていました。
一緒に起きた祖母も近くに行って止めようとすると祖父は、祖母と目を合わせながら、「もう死ぬからな。迷惑かけたな。ありがとう。」と言い、それから目を瞑ったまま何も言わなくなりました。
私は慌てて「おじいちゃん、ありがとう!お疲れ様!」と衝動的に叫びました。亡くなる人も聴覚は最期まで残ります。最期は本当に今にも喋り出しそうなくらい、穏やかな顔でした。
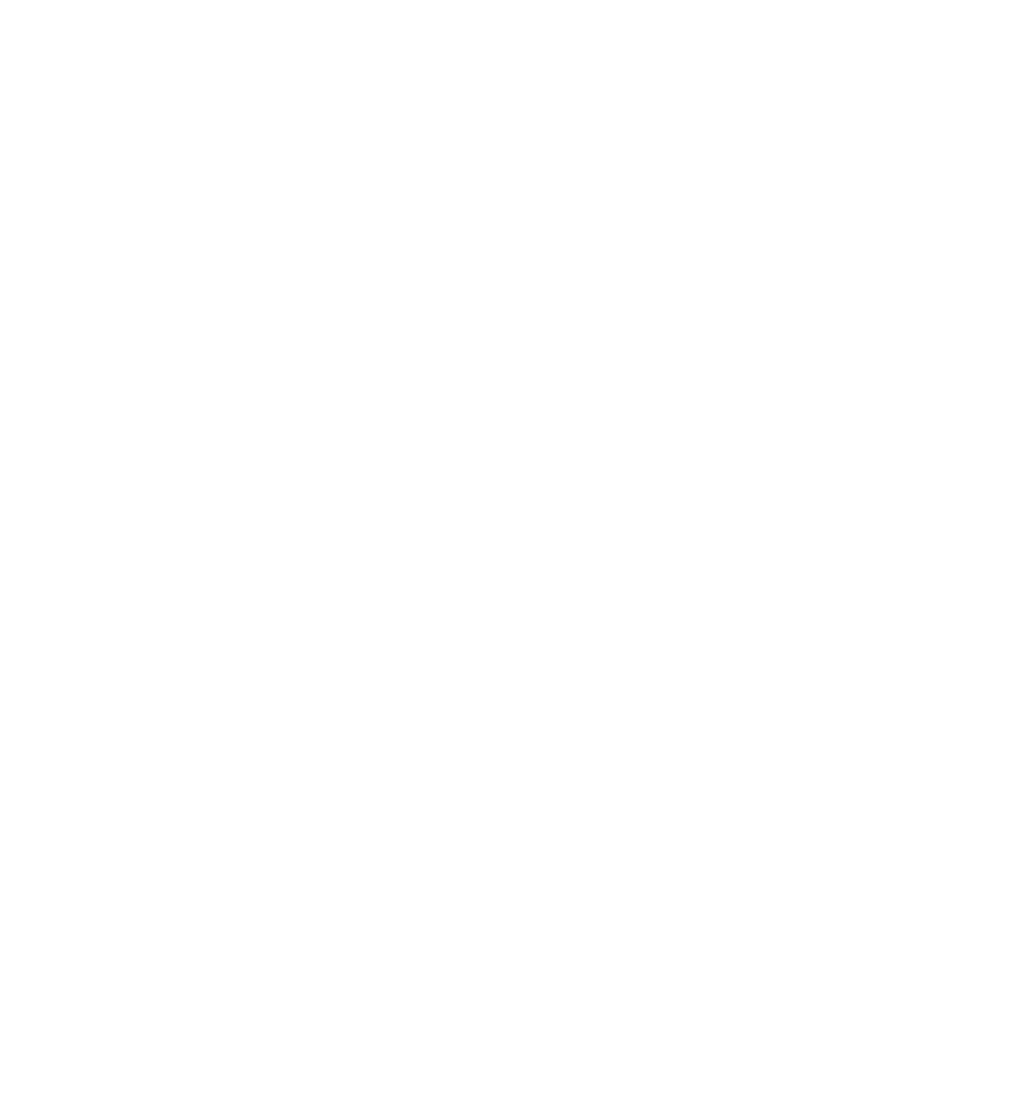 ご本人はどんな方でしたか
What kind of person was he
ご本人はどんな方でしたか
What kind of person was he

 病気はどんな経過を辿りましたか
How did the disease progress
病気はどんな経過を辿りましたか
How did the disease progress

 やってよかったこと
What are you glad you did?
やってよかったこと
What are you glad you did?

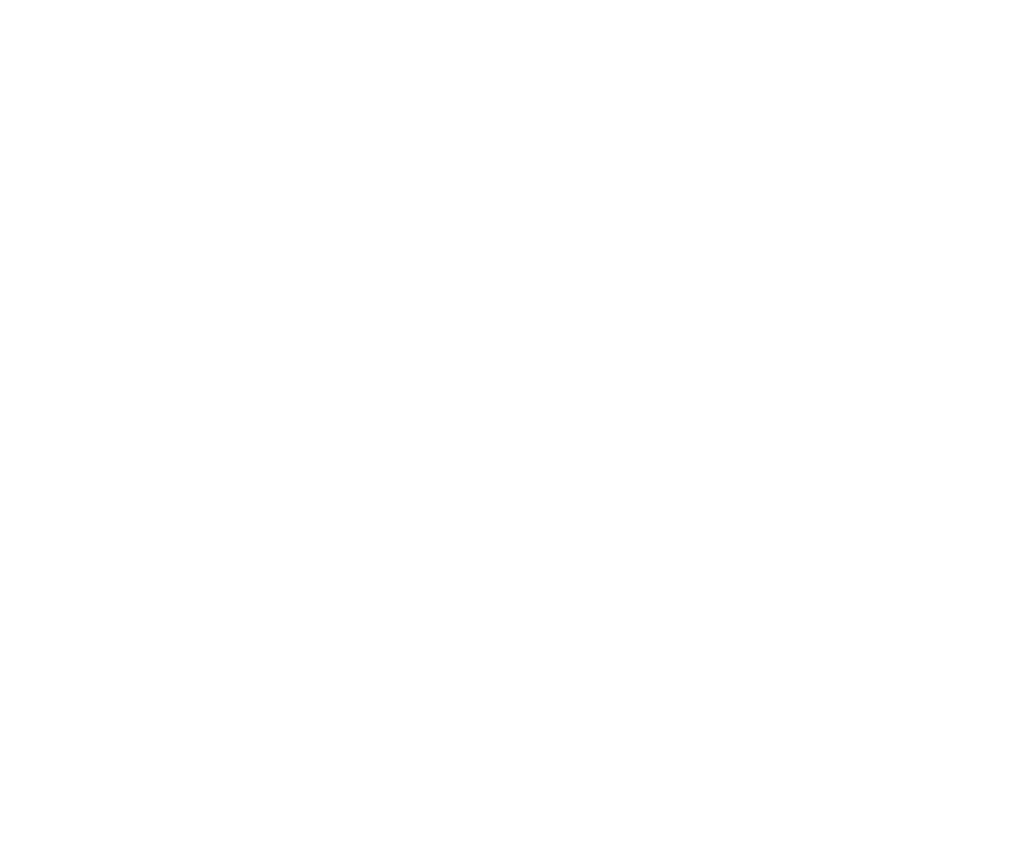 もっとこうすればよかった
Things I'm glad I did
もっとこうすればよかった
Things I'm glad I did

 もっとこうだったらいいのに
I wish it was more like this
もっとこうだったらいいのに
I wish it was more like this

 この先 家族を看取る方へ伝えたい事
What I would like to convey to those who will be caring for their families
この先 家族を看取る方へ伝えたい事
What I would like to convey to those who will be caring for their families


































