「最後のタバコ」
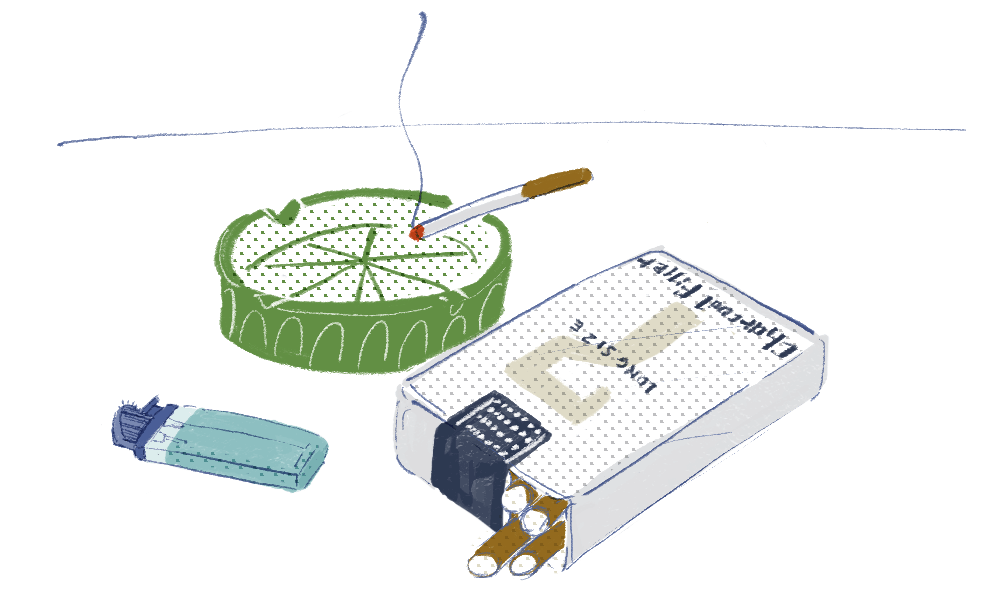



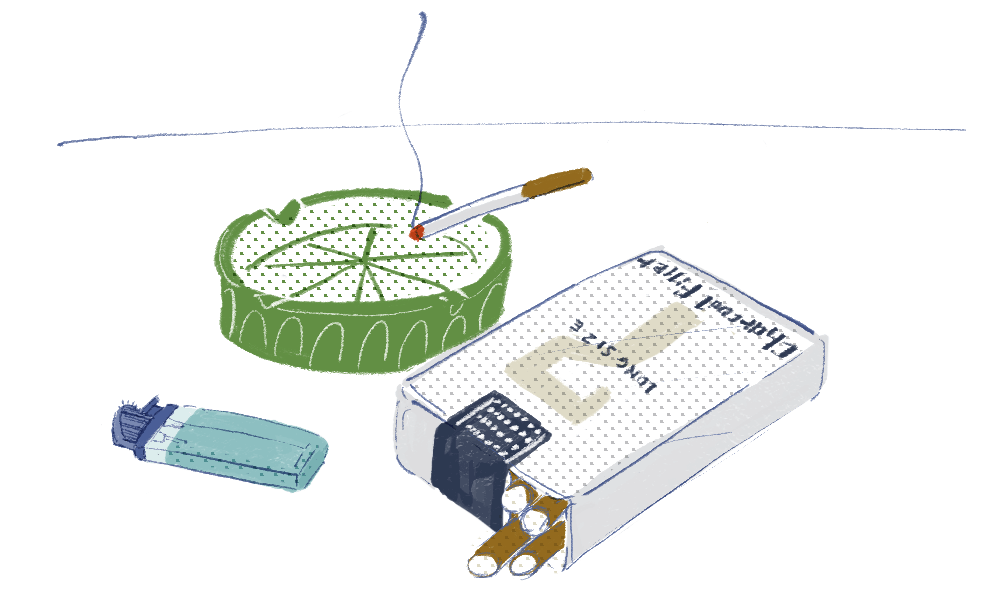
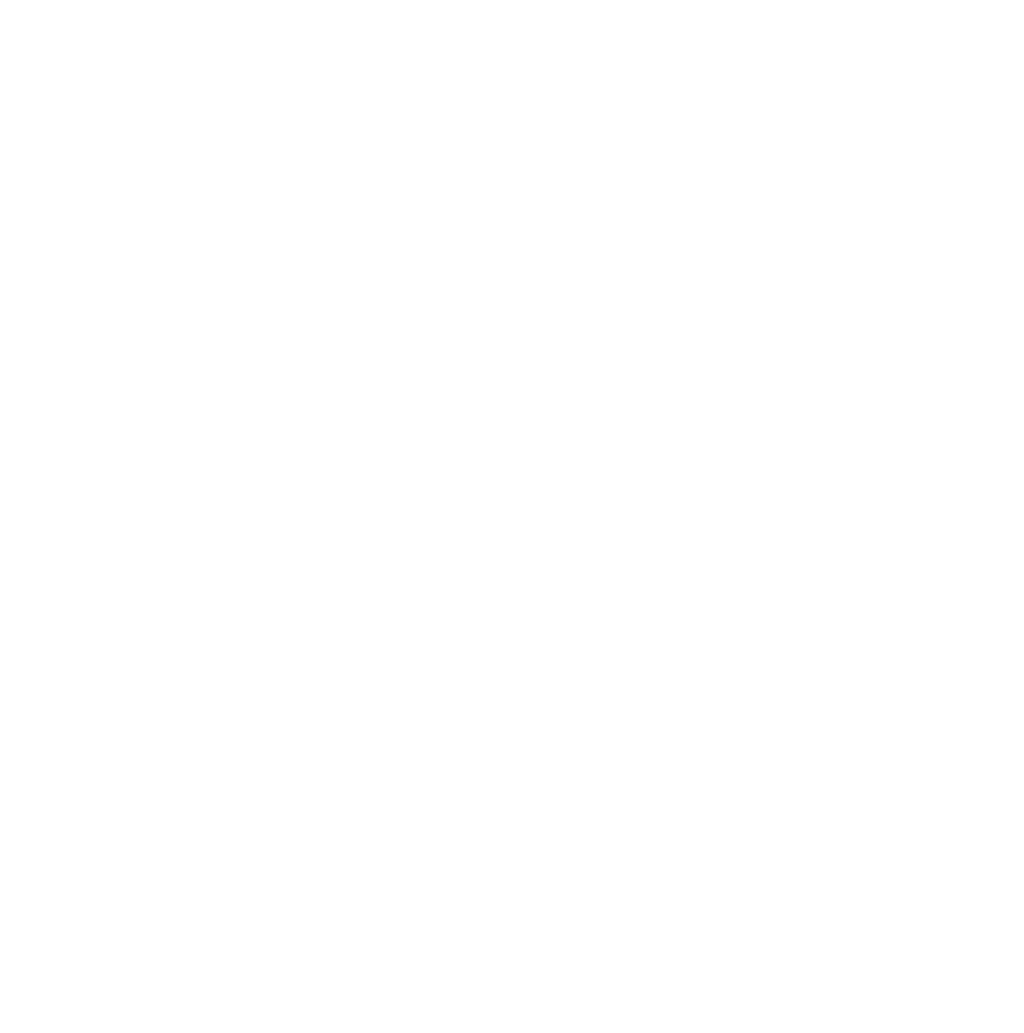 どんな看取りだったかお聞かせ頂けないでしょうか
どんな看取りだったかお聞かせ頂けないでしょうか
Aさんは、76歳の時に大腿骨を骨折、緊急手術を行いました。手術後すぐにリハビリ目的で介護老人保健施設へ転入したのですが、2週間ほどで自己退所されてしまいます。足の機能が回復しないまま、高齢の姉との二人暮らしを選択されます。
担当ケアマネジャーの訪問も拒否し、引きこもり状態が続きました。2ヶ月後に同居の姉の認知症が発見され、姉の施設入所が決まります。この時に、不衛生な布団の中で生活しているAさんが発見されました。重篤な床ずれもあり、緊急入院を勧めますがAさんは断固拒否。
急遽、地域の医療福祉介護で連携を組み、Aさんの独居での在宅療養を支える方針が決まりました。Aさんを説得し介入できた介護保険サービスは、訪問看護と訪問介護だけでした。私はここから、Aさんとの「訪問看護師と利用者」という関係がスタートします。
実際のAさんの生活は、足の障害と円背(えんぱい)の進行で、伝え歩きができる範囲の狭い空間が日常の暮らしでした。思い通りに動けない、慣れない環境への苛立ちからトラブルになることも多く、生活リズムが整うまでには時間を要しました。
ただ、それらを乗り越える度に、Aさんと訪問看護師、訪問ヘルパーとの信頼関係が深まっていきました。この生活は、この後、8年間も継続する事ができました。
84歳になった頃から認知症の症状が現れ、頻回の転倒が見られるようになり、私たち訪問看護師や訪問ヘルパーは独居生活の限界が近いと感じていた頃です。Aさんにも「夜は心細いし怖い」「もう少し一緒にいてくれないか」と“ひとりでいることの怖さと寂しさ”を吐露し始める変化が見られました。
ある時、Aさんの服や枕にタバコの焦げ跡を見つけた私は、これがタイミングと考え、独り暮らしを終わりにしないか、そして施設へ行かないかと話をしてみました。
「Aさんを火事で死なせたくない」「Aさんをひとりで寂しく死なせたくない」と踏み込んだ本音で話をすると、Aさんは真剣な眼差しで「私も私の頭がバカになって来ているみたいで、ひとりはもう無理かもと思っていた。もうこの家を出てもいいよ。そのかわり時々は私の顔見に来てほしいけど」とのことでした。これを機にAさんは施設へ入所されました。
施設でのAさんは車椅子の自操をマスターし、広い施設を動き回り、別の入所者の部屋を訪問して世話を焼いたり、若いスタッフと笑顔で談笑をしたりと別人のようでした。「夜が怖くないから、まあまあここも悪くない。タバコを吸わせてくれないのだけは不満やけどね」と毎回言っていました。
入所して1年頃に肺炎を発症し、そのまま寝たりきりの状況になりました。
私がAさんの元に向かった時には、すでに意識が混濁している状況でしたが、私のことは認識してくれました。何となく「Aさん、久々にタバコ吸う?」と聞くと、微かにAさんがうなずきました。
スタッフのタバコを1本もらい、火のついていないタバコをAさんの口元に持っていくと、タバコを2、3回噛んで、右口角に斜めに構える独特なくわえ方を久しぶりに見せてくれました。
懐かしいなあと思いながら、「Aさん、久々のタバコ美味しい?」と聞くと、「ま・・・ず・・・い」とかすかに言って、ニヤッと笑いました。しばらくして舌で押し出すようにタバコを吐き出し、またニヤッと笑いました。
そしてそのまま、ゆっくりと深い眠りに入っていきました。息が止まる瞬間まで私は手を握り、Aさんを看取ることができました。
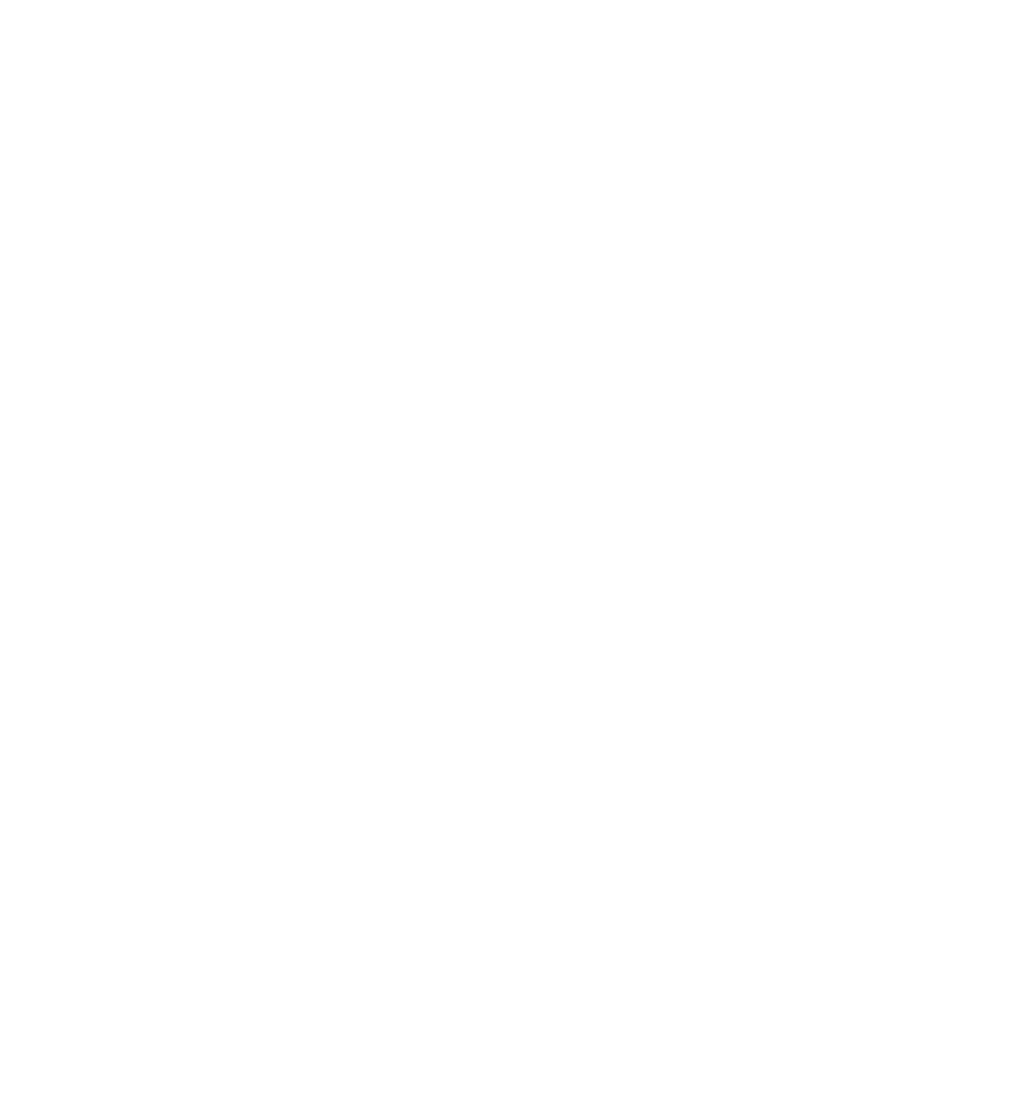 ご本人はどんな方でしたか
What kind of person was he
ご本人はどんな方でしたか
What kind of person was he

 病気はどんな経過を辿りましたか
How did the disease progress
病気はどんな経過を辿りましたか
How did the disease progress

 やってよかったこと
What are you glad you did?
やってよかったこと
What are you glad you did?

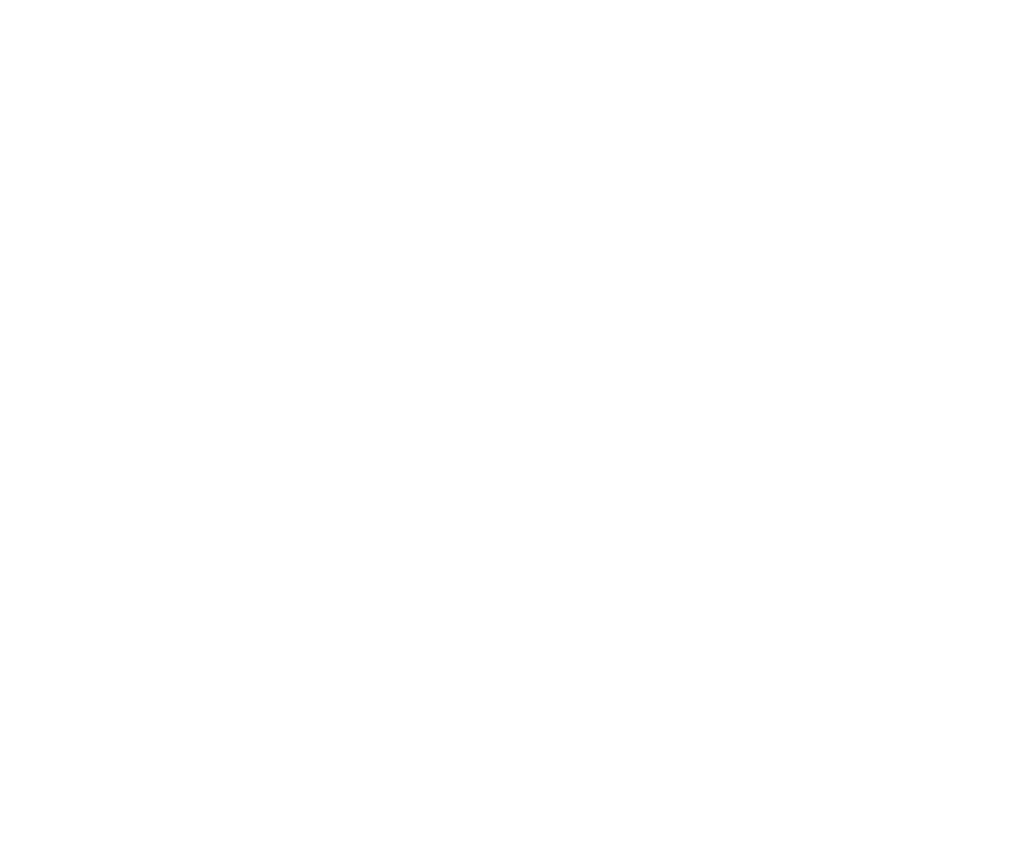 もっとこうすればよかった
Things I'm glad I did
もっとこうすればよかった
Things I'm glad I did

 もっとこうだったらいいのに
I wish it was more like this
もっとこうだったらいいのに
I wish it was more like this

 この先 家族を看取る方へ伝えたい事
What I would like to convey to those who will be caring for their families
この先 家族を看取る方へ伝えたい事
What I would like to convey to those who will be caring for their families

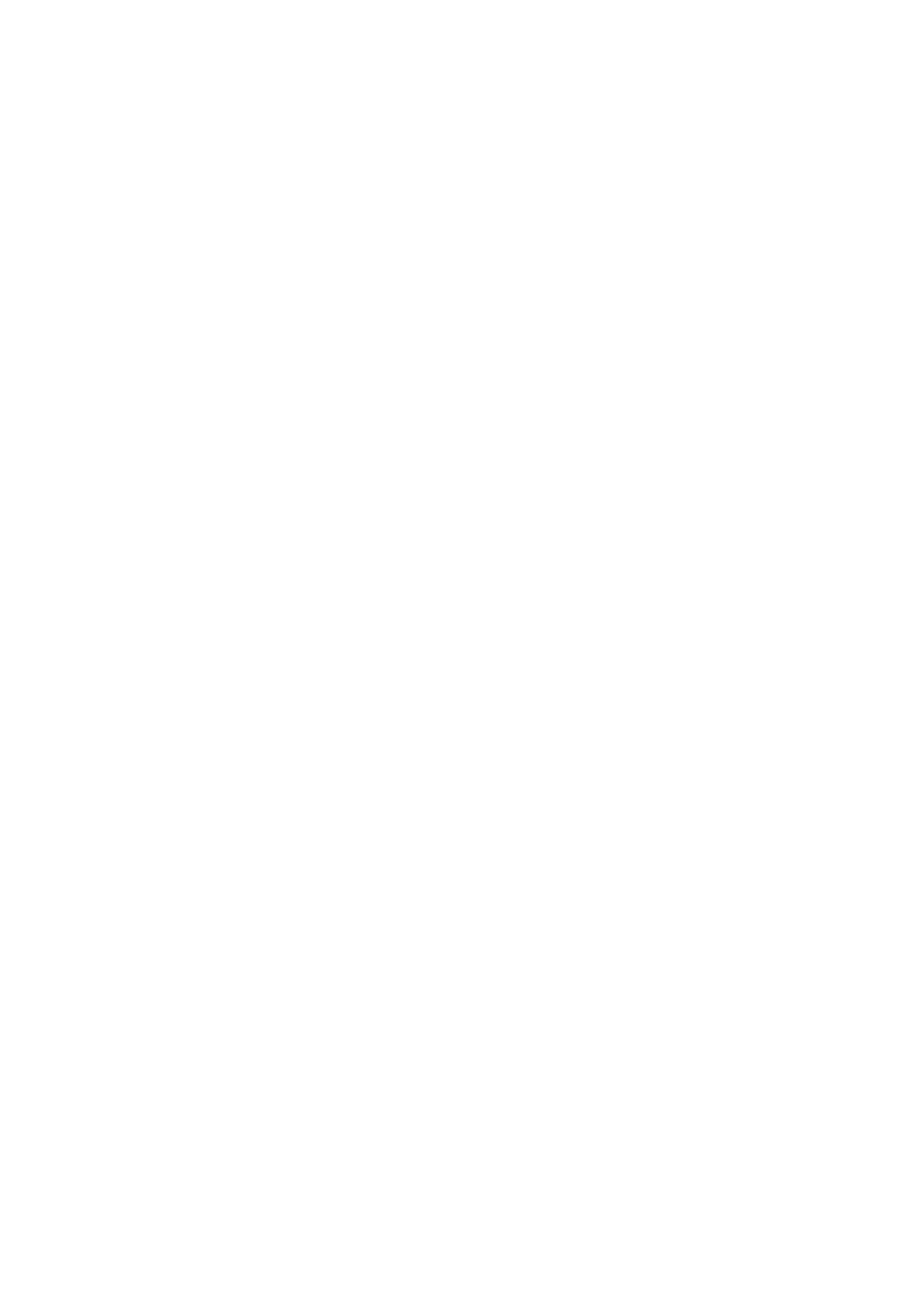 旅立ったご本人へのメッセージ
A message to the person who has departed
旅立ったご本人へのメッセージ
A message to the person who has departed


































