父の最後は日々の暮らしの中で ~ 娘が語る 父の旅立ちの物語 ~





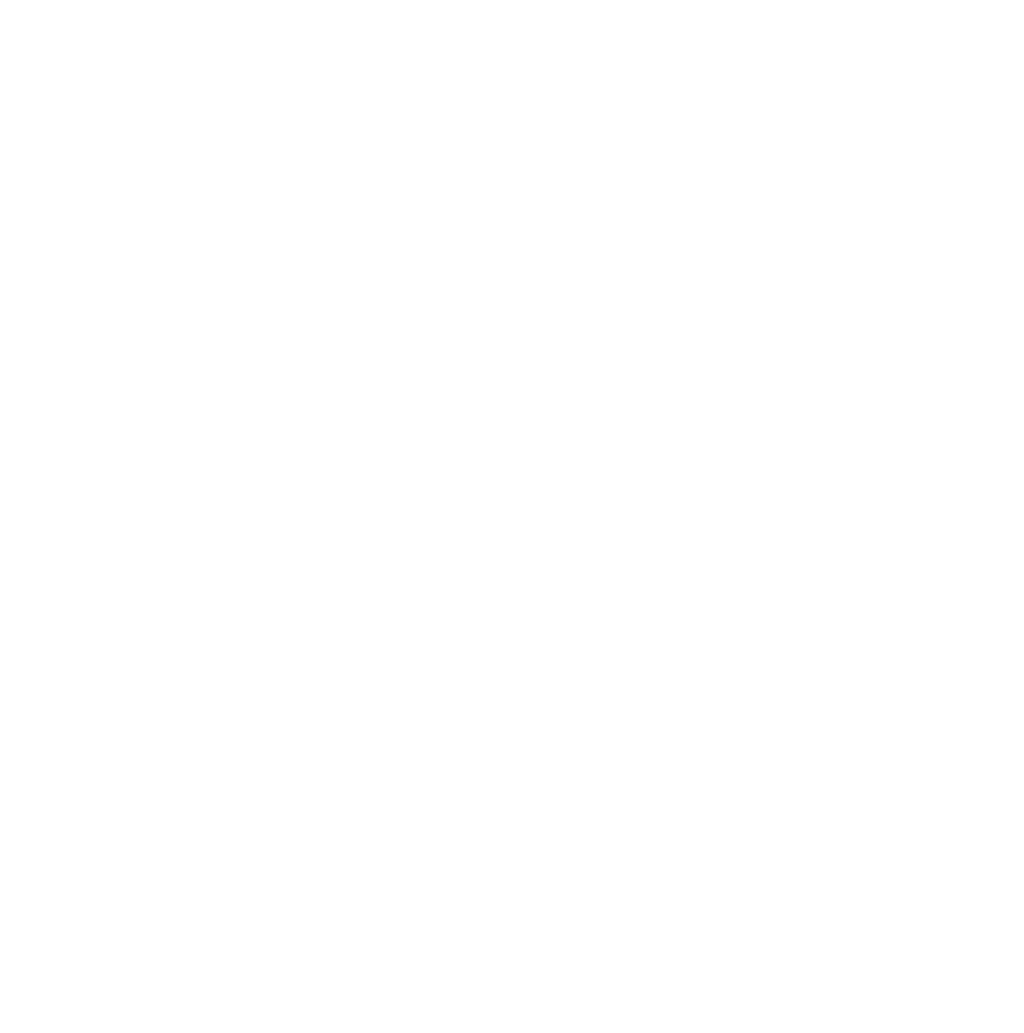 どんな看取りだったかお聞かせ頂けないでしょうか
どんな看取りだったかお聞かせ頂けないでしょうか
平成29年9月1日、真夏の残暑は厳しかったけれど、朝から良い天気で爽やかな風の吹いている日でした。「お父さんおはよー」と寝室の扉をあけ、カーテンと窓を開けて風を入れ、母も兄も、それぞれに食事を作ったり家庭ゴミを出しに行ったりして、今日もまたいつもの日常が始まるはずでした。
父の顔を覗き込むと、昨夜の苦しげな呼吸もようやく治まったようで、穏やかに寝息をたてていました。「お父さん落ち着いたみたい」そう言って食卓についたのです。
10時。そろそろ目が覚めたかなと様子を見にいってみると、誰も気付かないうちに、父は自分のベッドの上で穏やかに息を引き取っていました。
「あれ?お父さん?」動かなくなった父はまるで眠っているようで、おそるおそる鼻に手をかざしてみました。「なによ…お父さんてば。」突然訪れた「その時」にも関わらず、自分が予想していたような気持ちの動揺は不思議なほど無いまま、母と兄にすぐに伝えに行きました。
二人とも「そっか」「うん」と呟くと父の居る寝室に向かいました。後で母から「何となく覚悟は出来てたしね。騒いだってお父さん生き返るわけでもないし。いつもの寝顔だったし」と聞いて「ああ多分私もそうだったのかも」と思ったものです。
あの時気持ちが揺れなかったのは、まだ目の前にパジャマ姿の父が居たからだったのか...。そう想いを巡らせながらしばらく呆けていましたが、何もしないで主治医の先生の到着を待つ訳にもいかず、手分けして親戚に電話をしたり、これから始まる通夜のために部屋を片付けたり。
そして肝心の父は、1時間近くもベッドの上に放ったらかしにされていました。「あー!お父さんゴメンね一人にして」と時折声掛けしつつも、顔にかける白布もないまま、とにかく主治医に先生が到着するのをひたすら待っていました。
ようやく先生到着。ひととおり聴診器を当てて瞳孔検査をして「じゃあ、死亡診断書を書きますのでね、あとで病院に取りに来てください」そう言ったあとに「がんばったねえ、章さん」と冷たくなった父に優しい声をかけてくださいました。
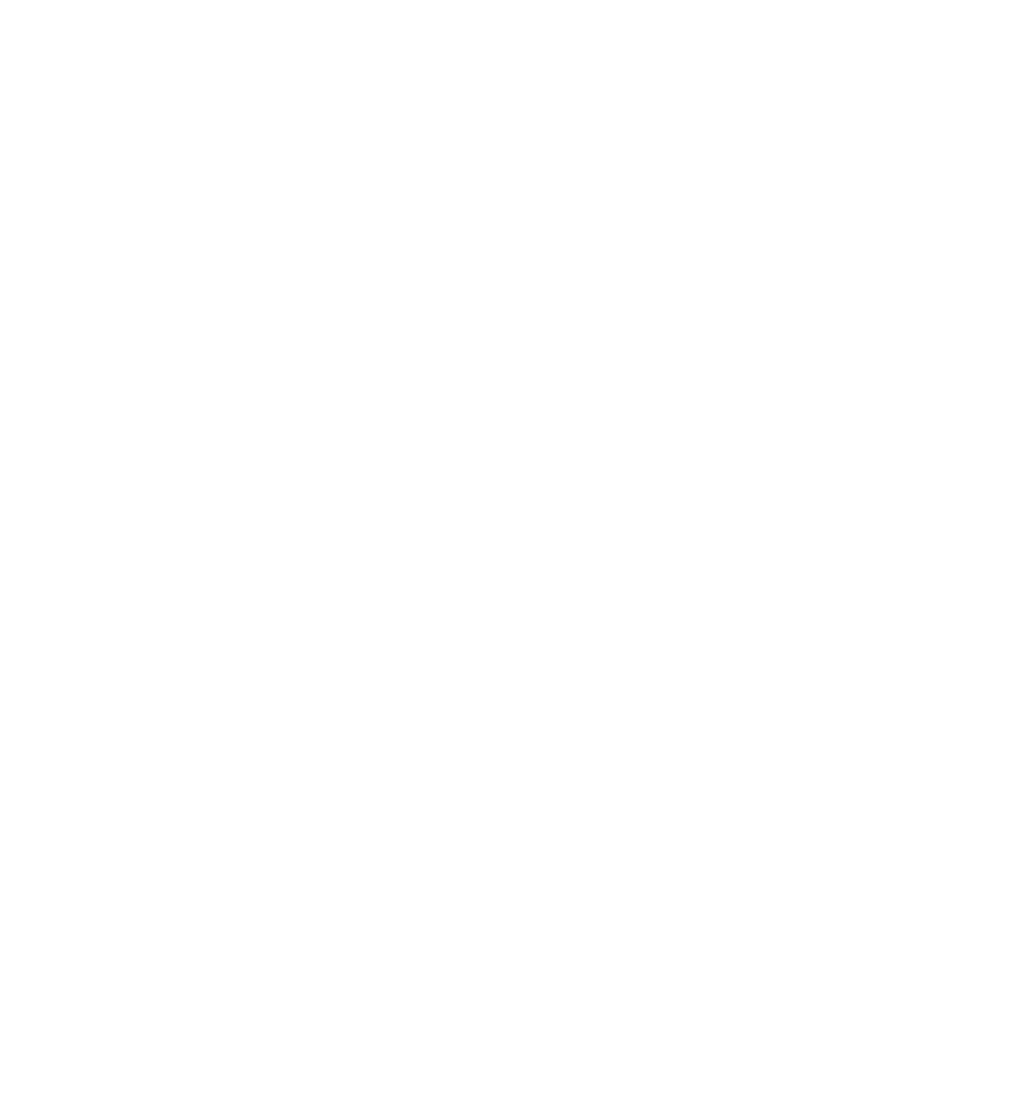 ご本人はどんな方でしたか
What kind of person was he
ご本人はどんな方でしたか
What kind of person was he

 病気はどんな経過を辿りましたか
How did the disease progress
病気はどんな経過を辿りましたか
How did the disease progress

 やってよかったこと
What are you glad you did?
やってよかったこと
What are you glad you did?

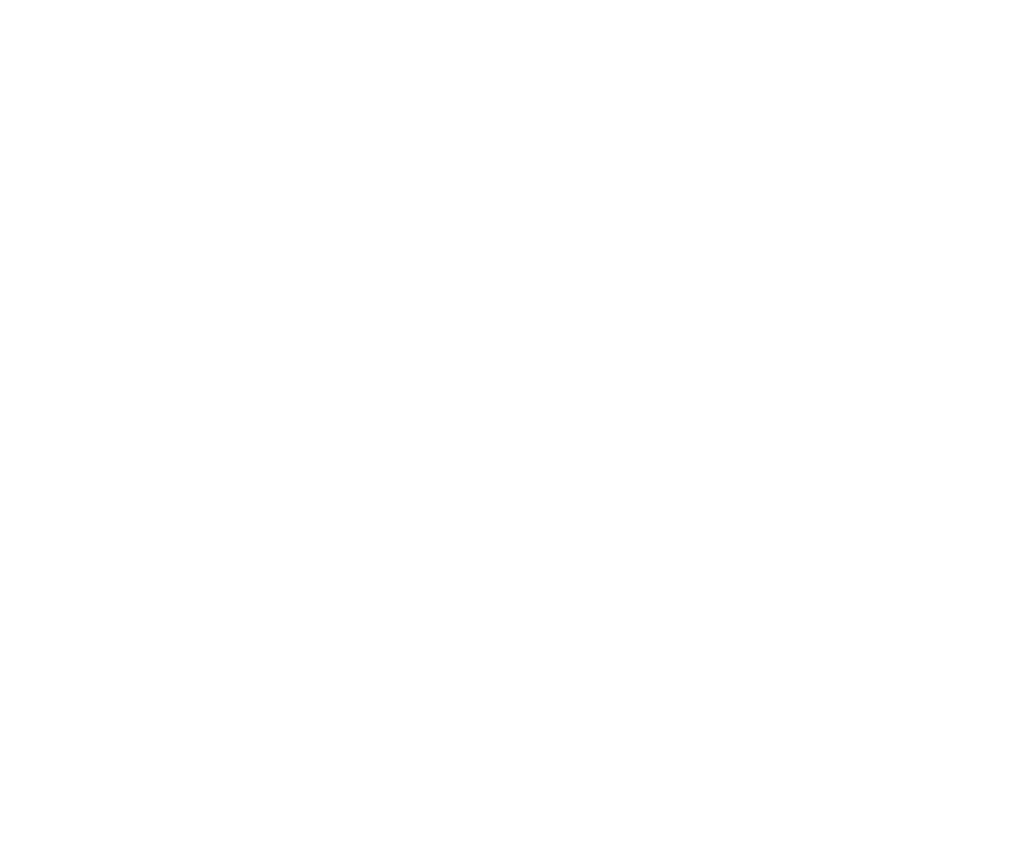 もっとこうすればよかった
Things I'm glad I did
もっとこうすればよかった
Things I'm glad I did

 もっとこうだったらいいのに
I wish it was more like this
もっとこうだったらいいのに
I wish it was more like this

 この先 家族を看取る方へ伝えたい事
What I would like to convey to those who will be caring for their families
この先 家族を看取る方へ伝えたい事
What I would like to convey to those who will be caring for their families

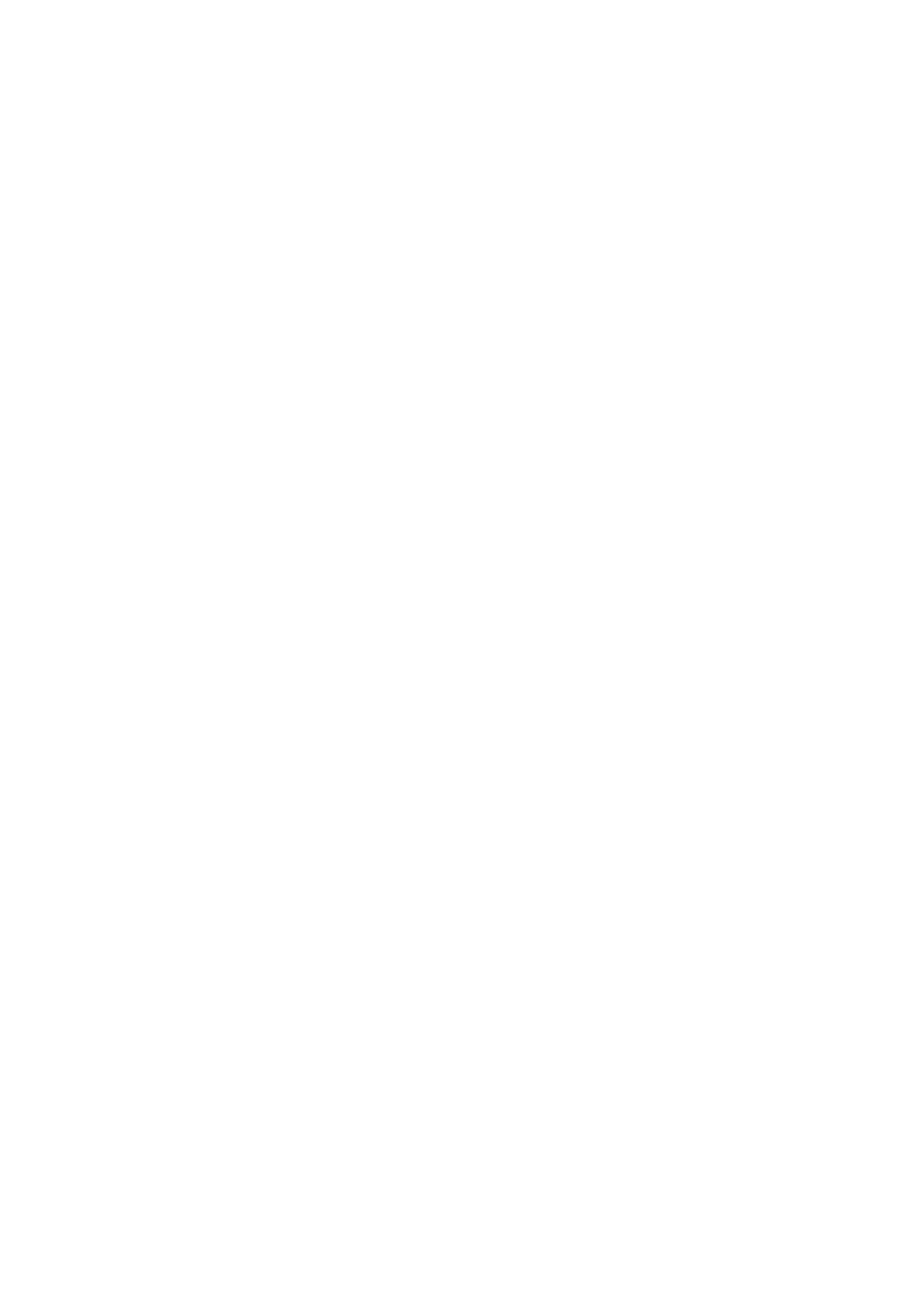 旅立ったご本人へのメッセージ
A message to the person who has departed
旅立ったご本人へのメッセージ
A message to the person who has departed


































