20歳の冬、父を看取ったあの日
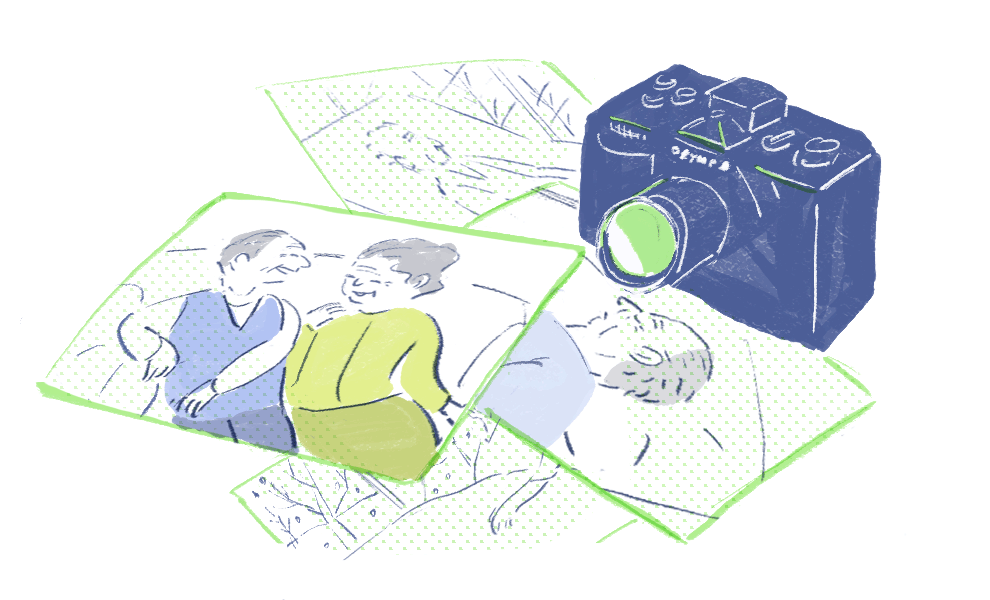



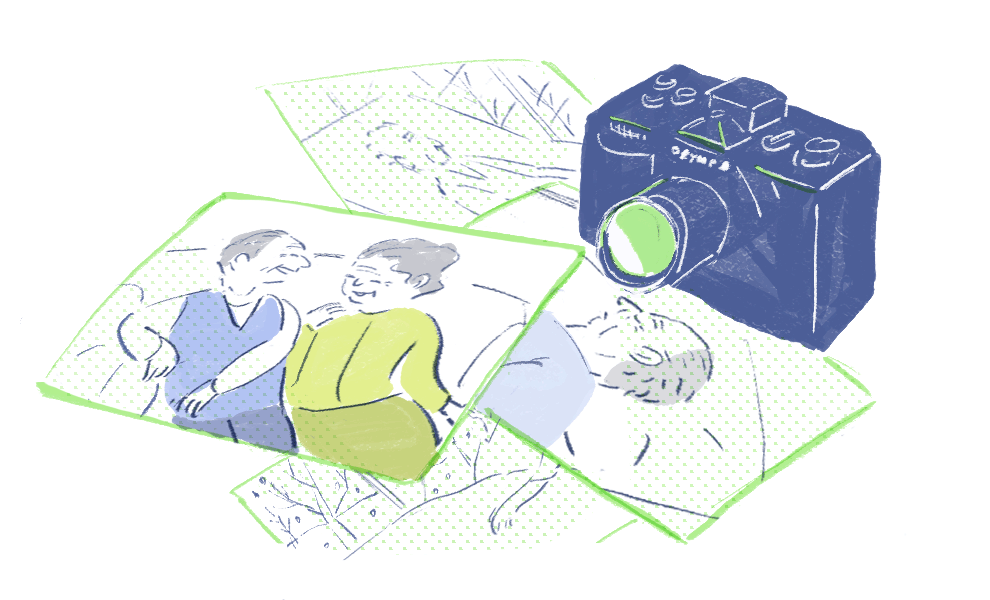
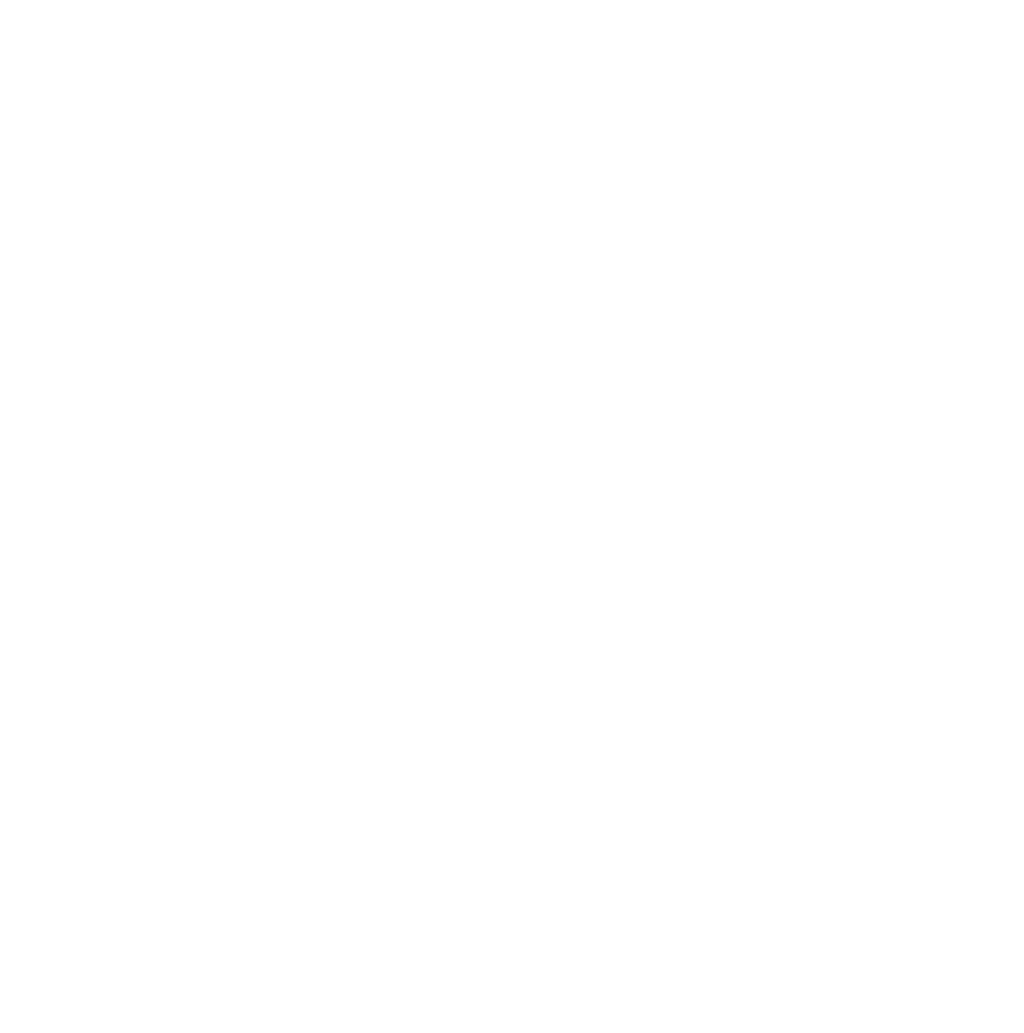 どんな看取りだったかお聞かせ頂けないでしょうか
どんな看取りだったかお聞かせ頂けないでしょうか
父の最後は地元の診療所で看取りました。
毎日毎日、仕事終わりに母と一緒に父に会いに診療所に行っていました。すれ違う車も少ない、診療所までの真っ暗な夜道を運転していると、心が蝕まれるような感覚になっていたのを今もよく覚えています。
病室に入って母と一緒に父にたくさん声をかけました。もうこの時はすでに父は受け応えができる状態ではありませんでした。
ですが、まだ意識はあり、父特有の小さくて子供のような目でじっとこちらを見つめ返してくれました。手を握ると、握り返してくれる時もあり、私と母の心は救われるような思いでした。
ただ、誤嚥性肺炎で入院しているため、肺炎が悪化しないよう何も食事ができず、お腹が減っているのか咀嚼する様に口を動かす父を見るのはとても心が苦しかったです。
そして、入院から1ヶ月も経たないうちにその時は訪れました。その日、私は仕事帰りにいつも通り父に会いに診療所に行きました。あの時、なぜか父の呼吸がいつもより荒かったのを覚えています。
(これは後に調べてからわかった事ですが、死前喘鳴というもので、亡くなる前の末期ガン患者におこる症状だそうです)一抹の不安を感じましたが、今日はたまたま具合が良くないのかもしれないと思い、そのまま帰りました。
それから深夜の2時、スマホに着信がありました。慌てて跳ね起きて確認すると、それは母からの電話でした。
母は昨日から診療所に寝泊まりしていたので、その日も診療所にいました。
「〇〇ちゃん、早く来て」切羽詰まったような母の言葉に私はついにその時が訪れてしまったのかと瞬時に理解しました。
胸が締め付けられるような思いになりつつも、冷静にならなくちゃと落ち着いて返事をしました。「わかった。親戚にもくるように連絡する?」というと母から「今はしなくていい」と返ってきました。
「お父さん息してない。もう......来ても遅いから」その言葉を聞いた瞬間頭が真っ白になりました。
母が私に電話をした時、すでに父は息を引き取っていました。母も看護師に起こされて気がついた時には父は息をしていなかったそうです。電話を切って急いで車をはしらせました。
あの日、診療所までの道のりが、いつもより異様に長く感じました。まだ肌寒い4月だったのに、異様に汗をかいたのを覚えています。
病室に駆けつけた時、母が父の病室に立っていました。病床に臥せる父はまだ眠っているかのようで、死の匂いを感じさせませんでした。
ですが、もう父は息をしておりませんでした。その姿を見た瞬間涙がこぼれ落ちました。
「お父さん、もう死んでいるの…?」母に問いかけると、母も涙を流していました。
いつかくるだろうと思っていた瞬間が、思っていたものとは違う結果に終わってしまい、私と母はショックでした。父と最期の時を過ごしたかった。
父が逝くのを見守りたかった。それは今でも思うことです。
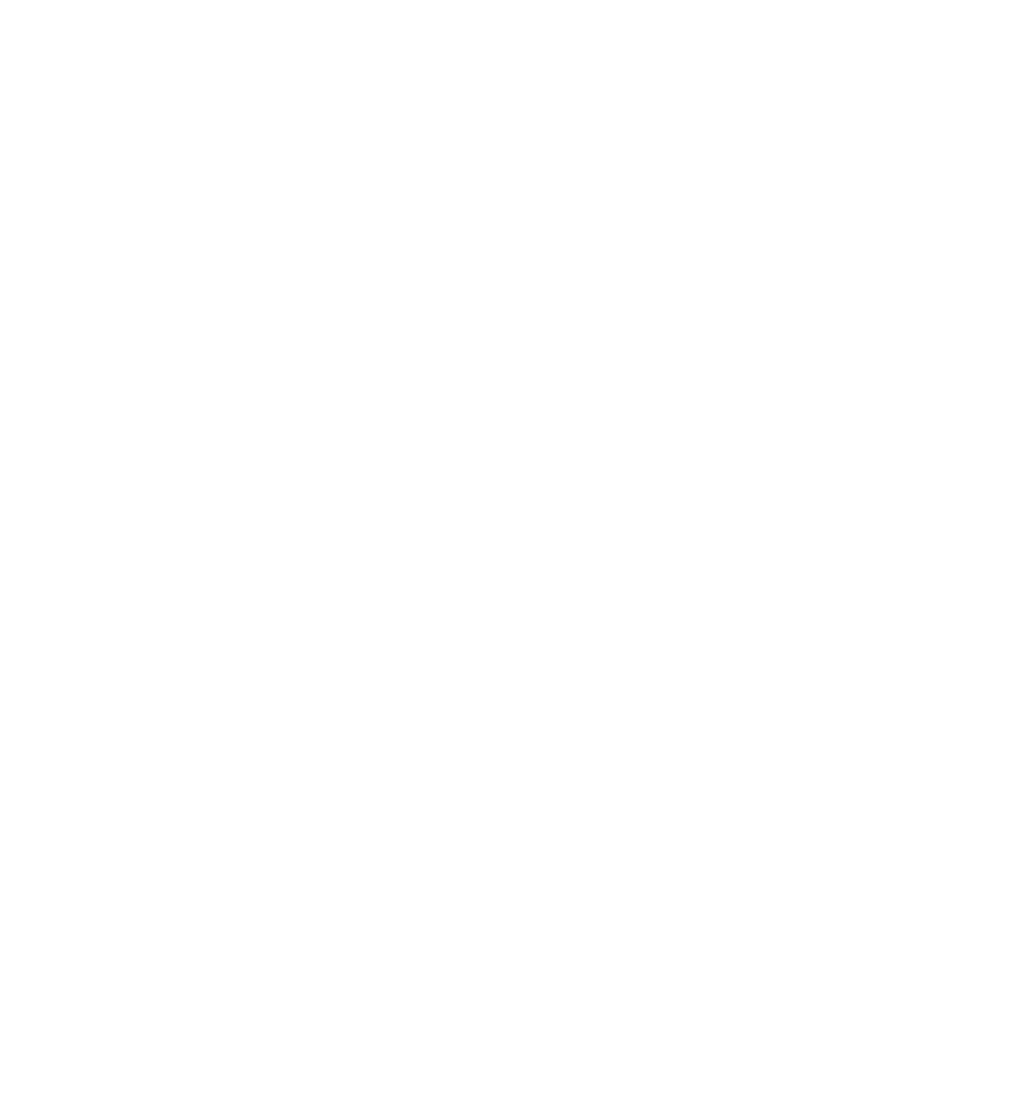 ご本人はどんな方でしたか
What kind of person was he
ご本人はどんな方でしたか
What kind of person was he

 病気はどんな経過を辿りましたか
How did the disease progress
病気はどんな経過を辿りましたか
How did the disease progress

 やってよかったこと
What are you glad you did?
やってよかったこと
What are you glad you did?

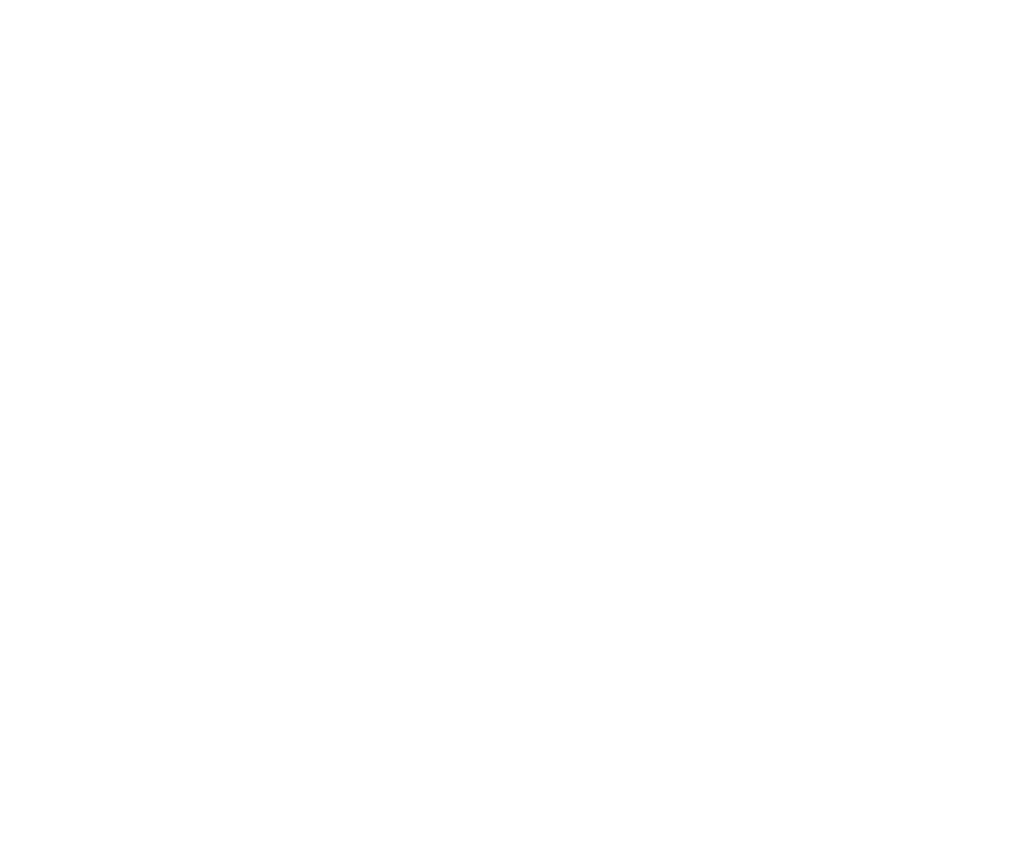 もっとこうすればよかった
Things I'm glad I did
もっとこうすればよかった
Things I'm glad I did

 もっとこうだったらいいのに
I wish it was more like this
もっとこうだったらいいのに
I wish it was more like this

 この先 家族を看取る方へ伝えたい事
What I would like to convey to those who will be caring for their families
この先 家族を看取る方へ伝えたい事
What I would like to convey to those who will be caring for their families

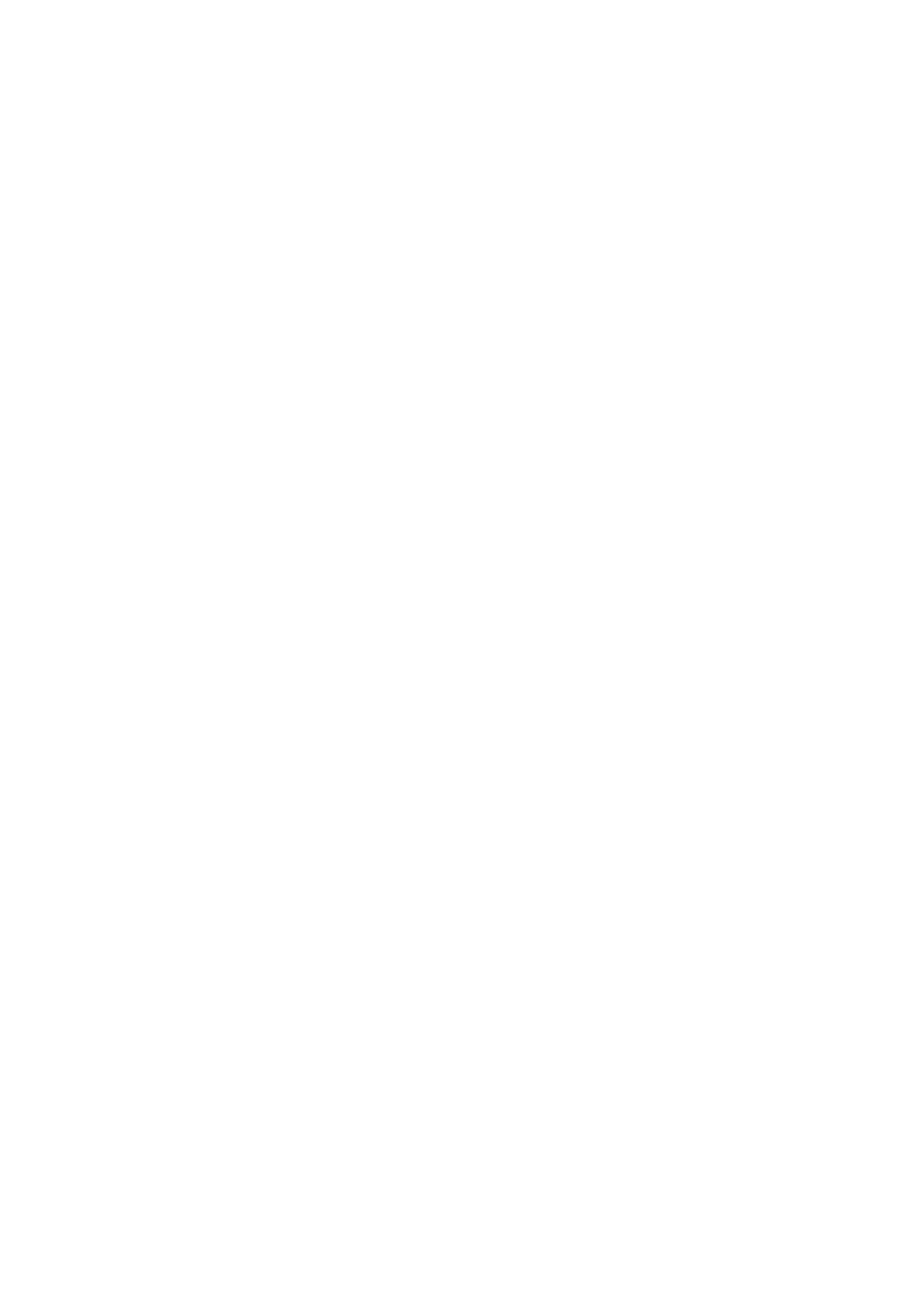 旅立ったご本人へのメッセージ
A message to the person who has departed
旅立ったご本人へのメッセージ
A message to the person who has departed


































